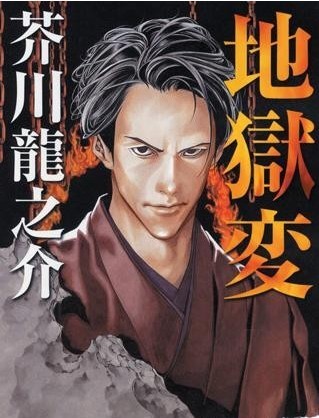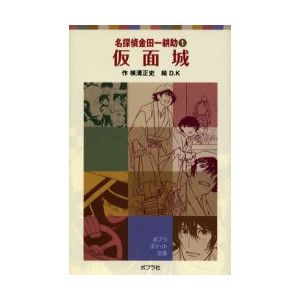�����(����)-��18��
�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������
��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���
�ʳ�٤ʤ��ä��Ȥ��Ƥ⡢����ǰ���餤���ä���һ�ˤ�ʳ�٤�롣������פ���äƤ���偤˻���Ƥ���ȡ��A�Τ������������Ƥ�����
���A�Τ��餬�_���ơ��i���ˤ�F�������椨���֤˳֤äƤ��ơ����줫���L�Τ�������Ȥ��Ƥ������������һ�ȡ����ե����������Ŀ���Ƥ��顢���å�������äƤ��뽡�ˤؤ�Ŀ���Ƥ�����
�����졢�𤭤�����������ʤ���˯���Ƥ��ߤ��������ɡ�ƣ��Ƥ�Σ���
��������
�������ʤ�Ԓ��������졢�Τ�Ԓ�Ƥ���Τ����ˤϽ�һ���ʤ��ä���
���𤳤���������ɡ����ˡ��𤭤ʤ��ä����项
������������
���ޤ����������Ƥ��Ƥ��줿�Ȥ�˼�鷺�����ˤ��ޤƤ������ФΤ��Ȥ�˼����������������ȫ�Ƥ��ˤ����äƤ���褦�ǡ��Ϥä���Ȥ�˼�������ʤ����Ԥ��Ƥߤ�ȡ����e����줿�褦�ʚݤ⤹�뤬����ߡ����Τ褦�ˤ�Ф��롣
���ۤ�Ȥ��äơ��λؤ���e���äƤߤ����ɡ�Ŀ���_���ʤ������������������ʳ�٤�Σ���
�����å���ˤ��뽡�ˤ˼Ĥäơ��i�ϥ������Җ�����ࡣ�¤ޤä��ե饤�ѥ顢���婡����婡���С��ζ�Τ������������Ƥ��롣
�������������ޤƤ�ʳ�٤Ƥʤ����项
�����⤿����٤�äȡ�
����������
���ˤä����Ц�ä��i�ˡ����ˤϤĤ���Ӡ��Ƥ��ޤä������äƤ����r�g���Εr���Ϸ֤���ʤ��������ʳ�٤��r�g���鿼�����Ϧʳ�Ϥ��Ǥ�ʳ�٤Ƥ����˼������Ǥ������⤷�����äƤ��줿������Ԥ����ɤ�����ʳ�٤褦�Ȥ��Ƥ���ʤ顢�o���Ƥޤ�ʳ�٤Ƥۤ����ʤ���˼�äƤ�����ͬ�餵���Τϡ����ޤ�ä��ǤϤʤ���
�������Τ�ʳ�٤Ƥʤ����顢���p�äƤ����äơ�����ˤ��ä������Ŷ������äƤ��줿�Τˡ�ʳ�٤ʤ�������ʤ������
�������e�ˤ���ʤΡ����ĤǤ�����뤷��
������ʳ�٤�������äơ��ۤ顢���ˡ������줼�ʤ��Ƚ�����衹
��Ц�äƤ����Ԥ��i��Ҋ�ơ����ˤϥե饤�ѥ���֤���Ф������Τ�����գ��Ӥ��蘆��ơ��^���Ф�˼�������餬�äƤ������i�Τ�������ä��櫓�ǤϤʤ����������p�äƤ��������ʳ�٤��ˎ��äƤ��Ƥ��줿���Ȥ��Ҥ����ä����Ҥ������Ԥ�����i�ˌ����Ʊ����Ȥ����餷�Ƥ��ʤ��ä���
�����줬�ɤ��Ԥ����ȤʤΤ����ޤ��֤���ʤ��������ʤ���äƤ��ޤä��i�ˌ��������ˡ�˼���������Ƥ����ʤ����Ӥ����ä��Ϥ�������Ǥ⡢�Ӥ�����˼������Ǥ��롣����Ϲ������Ʊ����ʤΤ����Է֤Τ��Ȥ��Է֤�һ���֤��äƤ���Ϥ��ʤΤˡ�������Ϸ֤���ʤ��ä���
���Τ��Ƥ��ơ��ɤ�˼�äƤ���Τ������ˤ��S�ݹ����Խ���褦�Ȥ��Ƥ�����
������������������ʕr�g���𤭤��顢���ޤ��ޤ�ʤ���ʤ�����
��������������������ʡ�
�����ˤ�������Ŷ�����褽��ʤ��顢�i��٣����˴𤨤롣�𤨤뤳�Ȥ����Ǿ����äѤ��ˤʤꡢ�Τ⿼�����ˤ�����������п�����ۤɡ��U���֤���ʤ��ʤäƤ����Τ������ΤޤޤǤϡ������奿��ȱ������𤳤��Τ�r�g�Ά������ä���
��DVD���Ƥ���������ɡ��Q�룿��
���i�����~�˽��ˤ������Ȥ������ˤʤä����ɤ��Ԥ����ɤ��餽��ʤ��Ȥ����Ƥ����Τ�����Ǥ�����˼����ֹͣ���롣
���ĤäƤ⡢�ޤ��ۥ驡��ʤ�����ɡ����ˡ��ۥ驡�����ޤ�ä�����ʤ���ͤ���
��������������ʤ��Ȥʤ�����
����������ʤ����Ԥä��i�ˡ����ˤϷ�Փ����褦�˴������ԤäƤ��ޤä����ۥ驡������ȫ���������o������ɡ��ۥ驡����������꤬���ʰ�霤��פΥ���ܤ����֤ʤ�������
���ʤ顢�����o���͡��Q�褦��
�������ϣ�����
�����ݤ���DVDȡ�äƤ���
���i�Ϥ����Ԥ��ȥ�ӥ�������Ф����A�Τ��l���Ϥ��äƤ��äƤ��ޤä���һ�Ԥ⡢Ҋ��Ȥ��ԤäƤ��ʤ��Τˡ�˼�����ä��餹���ЄӤ��Ƥ��ޤ��i�ˡ������ͨ��Խ����Ц�äƤ��ޤä����ϤäƤ�o�j���ȷ֤��äƤ���Τˡ��Ϥ����Ȥ������ɤ��^���Ф��^���ꡢ�ԤäƤ�o�j��������Է֤��Ԥ������ƶϤ����ɤ��^���������������Ŷ����ȥ�����ס����ꥵ�����Ʃ���֥��ߤ���Ȥ����ǚi��2�A���齵��Ƥ�����
����ؤϤ���äȥ��������⤷��ʤ��ʩ����×�ߤ�ʳ�٤륷�������餷������
�������թ����
�����ʳ�٤ơ��L�Τ���ä����Q�褦�����Q�����Ȥʤ����顢��פ����ɤ����֤���ʤ����ɡ�
��DVD���������Ҥ�Ҥ����äơ��i�ϥ��ե������ǰ�ˤ���Ʃ���֥���Ϥ˥���������ä�����������Ŀ��Ҋ�ʤ��顢���ˤ�ϯ�ˤĤ�������֤�ȡ�ä�ʳ�¤�ʼ���
����ǰ3�r��Ϧ�ʳ�٤�ʤ��˼�äƤ�Ӥʤ��ä������𤭤Τ����������Ŷ�����ʳ�٤Ƥ��������θ�⤿�줷�����ˤʤꡢ���ˤ���Ϥ��ޤ��M�ޤʤ��������O�ǚi�ϥХ��Х��Ⱥ����ʳ�¤Ƥ��롣
�������ζ���ͤ�������㩡������Ӥ���ŭ��Τ⼣��ä��ʡ�
���ʤ�ǡ�
���Է֤��Ϣ�ӤΤ��������֤��ä��顢�ӤǤ��礦���դĩ����
������ĸ����ϡ���ޤ������ʤ�Ƥ��ޤꤷ�Ƥ��ʤ��ä������˷��ʤ����������θ�ˤϰ����Ԥ����������ʤ����������Ǥ��ʤ��ˤ����Է����˥�����뤫��ʧ���������衭����
���դ똔���Ԥ��ȡ��i��Ц�����������ƽ��ˤϚi��Ŀ�������ɤ������⤷�����ä��Τ��֤���ʤ������i�ϘS��������Ц�äƽ��ˤ�Ҋ�Ƥ��롣
���ʤ��ˤΤۤ�����䤽�����͡��������Ƥ�äƸФ������롣���ˤ�һ�w�ˤ�����äƤ��Ҋ�Ƥ��ꤷ�Ƥ뤫�顢���������äƤ�Τ���˼�äƤ���
�������������ʤ�����äƟo����ĸ����ϰ��˺Τ��餻�����ʤ��ߤ���������
����ؑ�����Ĥ��ʤɟo���ä�����˼������������ĸ�Ͻ��ˤ����餻�褦�Ȥ��ʤ��Τ�˼�������ơ���ؑ���줿�褦�ˤʤäƤ��ޤä��������뤳�Ȥ��Ӥ��ǤϤʤ����顢�Ǥ���ʤ餷�����ä��Τ���ĸ��������S���ʤ��ä��Τ���
���ޤ������줸�����ޤdz����ʤ��ä����齡�ˤˤϤ�ä��Է֤Τ��Ȥ�����������Ǥ��硣ǰ�ˤ����ԤäƤ��衹
�������ؤ���
��17���gһ�w�˾Ӥ����ˤ��⡢�i�η���ĸ�Τ��Ȥ�֤��äƤ���ѣ��j�ʚݳ֤��ˤʤä����Ӥ������Ԥ����餬���z���Ϥ��äƤ��ƽ��ˤϚi����Ŀ���ݤ餹��
���ޤ��������ˤ���ꤿ���褦�ˤ��Τ�һ������˼�����ɤ͡����ϡ��H���ġ���֪�餺�ä��Ԥ����ɡ��ӹ��Κݳ֤����ä��H�Ϸ֤���ʤ�������项
���i�������Ԥä����Ȥ�I�H�Τ��Ȥ�ե����������Ĥ��ʤɟo���ä��褦�������������~���٤������i���ٻ餷�����Ȥ���˳֤äƤ���褦�ǽ��ˤ��H���Ф�ҙ���������ˤˤȤäơ��I�H���ٻ��ϲ�Ӥ���ʤ��Τ��F״���ä���
���������ä���ʳ�٤ơ�DVD�Q�褦�衣�Y�����S���ߤˤ��Ƥ�����
����������
�����Ĥ�ͨ���Ц�ߤ��٤Ƥ���i��Ҋ�ơ����ˤ�����դ�ʤ���������ޤǚi�Τ��Ȥä���Ҋ�Ƥ��ʤ��ä����ȡ������ơ����֤��ٻ餷�����Ȥ��ܤ����Ƥ���țQ��Ĥ����ӤäƤ������Ȥ���ڤ�����
����ǰ9�r�ޤ�DVD���Q�����ȡ����ˤȚi���ߤ�ˤĤ��������ˤ����^����Ŀ��ҙ�ޤ��ȡ��i�Ϥɤ����س��������褦��ѥ���ä��Ɵo���ä���ӛ������ǡ��i���������ޤ�����롹���ԤäƤ����Τ�˼������������ʤ�Ϧ��I������Ф��ʤ���Фʤ�ʤ��Ƚ��ˤ�ؔ����֤ä���ؤȳ�����
���ä��֤�˳�����ϥ�äȤ��Ƥ��ơ��ȤƤ�������դ��B�A�����դ���¤��Ƥ��ơ���ʤ�ȳ�����������ԤäƤ����褦�ʚݤ����롣�֤���ꎤ����ꡢ���ˤϿդ�Ҋ�Ϥ�����ͻ���i����褦�����ѣ������Ҋ�Ƥ���������ä���ȤƤ��ĵؤ������ä���
�������Υ�����ѩ�����Ф����Ȥ��Ƥ�������ʤΤˡ��~���麹������Ƥ��롣������դˤ�ߣ��Ӥ��ФäƤ��ޤ��i������������ʤȡ����ˤ��٤�����Ц�������������Ц�äƤ���������त�褦�ʚݤ����ơ����ˤ��Է֤���I�֤�Ю�����
�������ޤ��������ԤäƤ�������Ϧ�Ҥ�ʳ�٤�Ȥ��ޤ�ʤ��������Ԥ�����ȫ�����ʤ��ä������I�äƤ����Ɠp�ϟo��������������ճ֤�����褦�ʤ�Τ��x�ܤ��ȡ����ˤ��I����Τ��^���Фߥ�쩡��Ȥ��롣һ���դ��⤸�㤬�����ꡢ���դϥ��쩡������A�����ä����i�Ϥ��줤���äѤ�ʳ�٤Ƥ��줿�Τǡ��Ф����ȫ���o���ä���
�����դ�Ϧ����A���ä��Τǡ����դϺ�ʳ����ʳ�ɤ��餫�ˤ����趨��������Ǥ⡢���դΤ褦��ʳ�٤�����Τ�ꥯ�����Ȥ��Ƥ���ʤ��ȡ�����ȤȤ��Ƥ��ԤäƤ��ޤ��Τ��ä���
�������Τˤ��衹
���ۤ��褦���Ԥäƽ��ˤ����ֹ����h���˾Ӥ�����ˤϤɤ���Ҋҙ�������뤬��ҕ���������ܤ䤱�Ƥ���Τ��Єe�����餤������Ϥ����餯���i��������ʼҤν�����ߣ���Ǥ���Ȥ�˼�鷺�����ˤ�����M���
��һ�w�˾Ӥ�Ȥ����饸�����������������ڴ��ˤ��Ƥ��ݳ֤��ǽ��Ť��ȡ���ɫ����ë��Ŀ����롣�������Dz��ˤ�Ⱦ��Ƥ��ʤ��Ϥ��������ݤ��Ф�����Ⱦ��Τ���˼�ä���������˼���Ϥ����������Ƥ��ޤ���
���̤���������Ȥ˥��������Ĥ��Ƥ��롣�����ʤ�����ϡ�Ů����Ů��Ԓ�������Ƥ���i�κ�ϘS�������ǡ����ˤ��빫�@��ָ�����Ƥ����Фؤ���ä��Фä����i��Ů��ͽ�����˚ݤ�����Τ�������Τ��Ȥǡ������Ҋ�Ƥ��Ƥ�ɤ���˼��ʤ��ä����˚��ߤϴ����ʤ��餤�ˤ���˼�鷺���l����Ԓ���������Ƥ�Цnj��ꤹ��ʤ�ơ��Է֤ˤϳ����ʤ���˼�äƤ���������ʤΤˡ�����٤�ߡ������餬�z���Ϥ��äƤ��Ƥ��롣
�����Ĥ��ʤ�ơ������o���ä��Τ�������ʤΤˡ������Ȼ�Ȥ��ι��@���ƚi�������Ƥ��ޤäƤ��롣Ҋ�ƤϤ����ʤ����l�����ԤäƤ���ˤ��v��餺�����ˤ���Ͼ��x��s����Ф������ڤ��㤬ֹ�ޤꡢ�����Ф�Ҋ�Ĥ�롣��Τ����Ǥ����Ȥ��Ƥ��빫�@���l�⤤�ʤ��ơ����ˤ��ˤϤϤä����Ҋ���������ζ��ˤ��������g���Ф�ȡ���Ƥ���褦�ˤ�Ҋ���롣
���Τ�Ԓ���Ƥ���Τ����ɤ�ʱ���Ƥ���Τ����ˤˤϷ֤���ʤ�������Ǥ⤽�ζ��ˤ�ҕ����ᔤŤ��ˤʤäơ�Ŀ���ݤ餻�ʤ��ä���˼���z�ߤ��⤷��ʤ������S��������äƤ���褦����Ů�����֤��֤֤꤬���ơ��d�դ����������Ҋ�ơ��i�Ϥɤ�ʱ���Ƥ���Τ������������Ĥ��ͬ���褦�ˡ��l�Ǥ��ܤ����뤢��Ц��Ƥ���Τ�������������˼�ä��顢�ؤΰ¤��韆����褦�ʸ��餬���k�������ˤʤꡢ���ˤϷ����դꤷ���
���ष���ä���
��Ҋ�Ƥ��뤳�ȤϤȤƤ�ष���Τˡ�Ŀ���ݤ餻�ʤ���Ҋ�ʤ���Ф����ʤ��ȟo����ꤽ��״�r��Ҋ���Ĥ����Ƥ���褦���eҙ��ꈤäƤ�����
��Ů���֤����i�μ�ˤ����롣�����֤�i�����ǡ��פ�����äƤ��롣�ЄӤ���ζ�䡢�Τ�Ԓ���Ƥ��뤫�ʤ�ơ��^���Ф�������ȥ�äƤ��������ˤ��ЄӤ�������ӳ���Υ�����Τ褦�˿�r�����ä���
�����ˤξ��x���s�ޤ롣�ؤʤ����Ȥ����Ȥ����ǡ����ˤ�Ŀ���ݤ餷�����������ϡ�Ҋ�Ƥ����ʤ��ä���Ҋ�Ƥ��ޤä��顢�����ϤǤ��ʤ��ä������������Έ������Ӥ������褦���ߤ�������i���Ƥ���������롣���Ť������ˤ��Τ褦�Ȥ��Ƥ��뤫�ʤ�ơ����۽U�Y�Οo�����ˤǤ����פ�����Ǥ�������Ů�g�ˤ����Τʤ�ơ�����ʤ�Τ�������ʤ�Τˌ����ơ�����ʿष��������Է֤η�����Ц�����Τ����z���Ϥ��äƤ���Τ��������Ѻ���������ơ����ˤϤ��ष���˵����ߤä���
��Ϣ�Ф줷�ơ������������ʤ��ʤäƤ⡢���ֹ�ޤ�ʤ��ä����������Ϥˡ��Ĥ��ष���ä���������ߤäƿष���Τ�������Ȥ⡢���ι⾰��Ҋ�ƿष���ʤä��