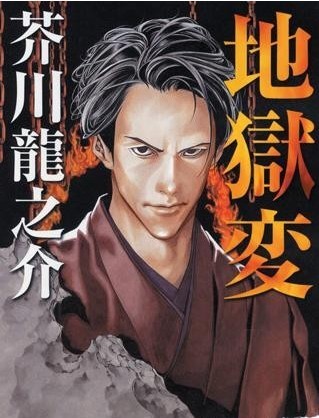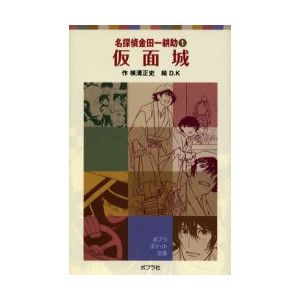�����(����)-��16��
�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������
��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���
Ұ���Ҥ��_���Ƥˤ���äƤ���Τ�Ҋ�ơ����ˤ��⤸�㤬�����뤳�Ȥˤ������⤸�㤬�Ϥ���ʤ˕r�g��������ʤ��������Ϥ⤢�꤭����ʤ�Τ��त��ĸ������Ȥ��Ƥ��������ǡ��褯ʳ�ˤ���Ƥ��뤬���ݤˤ��Ƥ�����ԣ�ϟo���ä���
�����ޤͤ��Ȥˤ��㥬�����Ƥ������ƴ��Ф롣�ե饤�ѥ���ͤ�������ţ���롣����̶ȡ���ͨ�äƤ�����ˮ�����ơ�ţ�⤫������֭��ȡ�äƤ���ˤ��Ͷ�뤹�롣���줫�饸�㥬����Ȥ��ޤͤ������Ƥ��顢�ơ��ߤ��ɰ�ǡ����礦�������ζ��գ����롣һ�B�����I�����Z��Ƥ��ơ�������������Ŀ�ˤ���ΤϾä��֤���ä�����Ҫ�I�褯�����������z��Ǥ����g��ζ��֭���������ȡ�Ƭ��偤��֤���Ф����l���ä����Τ��֤���ʤ�����Ƭ��偤����һ���Ϥ��ä���Ƥ��ƽ��ˤ��֤Ͻ줫�ʤ�������Ǥ�̨��ʹ�äƤȤꤿ���ʤ����ˤϡ�����Ӥ롣
���������á�
������һ�i�ǽ줭���������Ԥ��Τˡ����β���С��s�ޤ�ʤ������Į���֤������Ѻ���褦����Ф�����ָ�Ȥ�ȡ�äƤ��Ȥ˽줯������ȡ���֤����ʤ����B��褦�Ȥ����Ȥ��ˡ���������֤���ӤƤ���偤�ȡ���֤�������
�����죿��
��������������Ƭ��偤�֤ä��i�����äƤ��������x�Ͻ������g���ˤ������Ȥ��@�������Ʒ��꤬�����ʤ��ä����i���^�˥������Ƥ��ơ�ǰ���٤�ˮ���ΤäƤ�����ˮ��Τ������Ф��Ԥ��Τϡ������Ԥ����Ȥ��Ԥ��Τ���������Ҋ��ߡ����ʤ��Ȥ��Ƥ��ޤä���
���i�ϺΤ��Ԥ�ʤ����ˤ�偤�ͻ�������������졢ʹ����Ǥ��硹���Ԥ����ܤ�ȡ�똔�˴ߴ٤롣�o�Ԥ��ܤ�ȡ�ä����ˤ�Ҋ�ơ�ҕ������������ե饤�ѥ���Ф���äƤ���ߤ�Ҋ�Ĥ�ơ����դ�ϦƤ롣
�����դ�Ұ�˳����
����Τ�Ҋ�¤��⤷���i��Ҋ�ơ����ˤ�Ϣ���¤����������ɤ���ɤ�Ҋ���顢���줬Ұ�˳���ˤʤ�Τ��̤��Ƥۤ������餤�������줿�褦�ˡ������⤸�㤬���衹���Ԥ��ȡ��i�ϡ������ޤ��gߡ��������ȿ�Ц��������
�����Ӥ��������⤸�㤬����ζ������͡�
�������Ǥ⡢�ʤ����ʤ���ĸ������⤸�㤬�ϡ�
�����ˤ�偤�ˮ�����ʤ��顢���줿���Ȥϴ𤨤褦��˼�������¤Ƥ�����ĸ�������⤸�㤬�ϥޥ����櫓�ǤϤʤ��������Ĥ�Τ������ʤ���˼�äƤ������Κݤʤ������Ԥ��ȡ��i�ϡ������Ȥ����⤸�㤬�äƤɤ��ζ����������������С�����Ԥä������줬���Ȥ�ʤ��ä����ˤϚi���Ҋ�����������������Ǥ��ʤ��ä����ե饤�ѥ��Ҋ�Ĥ��Ŀ�ϡ��٤��������������ǡ�����ƤϤ����ʤ����ԤäƤ���褦���ä���
��ζ��֭�ϺΤˤ���Σ����ց����뤳�Ȥ���ʤ顢�ց������ɡ�
�����㤡���Ʃ���֥��ä������������ơ�
���֤��ä���
���Ȥۤɤα���������ʤ��m��Ҋ�����ˡ��i��Ц���ʤ��饭�å��������Фä���������L�ˡ���Ȼ��Ԓ���������դ�����ʤ�ơ�˼���⤷�ʤ��ä������줬��ͨ�ʤ�����������ɤ���ݤˤʤäƤ��ޤ������֤����~�������ʤ������դޤǤ�ꓐ����ä��Τˡ�����ʤ��Ȥ����ä������Ǥ�������äƤ��ޤ��Τ�������������⤳��⡢�i��Ԓ�������Ƥ��뤫�顢���ˤϴ𤨤Ƥ�����������i���ФǺΤ��仯�����ä��Τ����������Ʃ���֥���ä��Ƥ���i���٤�Ҋ�Ĥ�ơ����ˤ�Ŀ���ݤ餷����
���i���������ä��櫓�ǤϤʤ�������������Ƥ��顢���ˤ��٤����ġ����äƤ�����
�����㥬����˻�ͨ�äƤ���Τ�_�J���Ƥ��顢���ˤ�ζҊ�����Է֤����ä��⤸�㤬��ʳ�٤Ƥ���ȡ���Ϥ�ĸ���⤸�㤬�ϺΤ������ʤ��褦�ʚݤ����Ƥ��ޤ�ʤ��ä������äƤ���Ȥ������O��Ҋ�Ƥ��뤬��ȫ�Ƥ�Ҋ�Ƥ���櫓�ǤϤʤ����Τ����������Ƥ���Τ������������������ʤɤ��Ƥ��ʤ��ä�ĸ�Τ��Ȥ����顢���귽�ʤ������Ƥ��ޤäƤ��롣���θ�ˡ����ˤ����Ԥ������Ȥ��ʤ�������Ϥ����ĸ�餷���ȡ����ˤ�˼�äƤ�����
������⤸�㤬��褽�äơ�������ζ��֭�����Ƥ��������Ǥ˲���ˤϤ���褽�äƤ��äơ��i���Ʃ���֥��ߤ�Ǥ��롣���դ�Ϧ��⤸�㤬�ȥ��������ζ��֭�ξߤϡ���䤷�Ȥ狼�����Ǭ��狼����ä��Τǡ������ˮ�˽����Ƒ������e�������˽g�ä��Ƥ��Ƥ�����һ�Ĥޤ߷֡��狼������Ǥ������Ф����롣����٤������줼�Ƥ��顢ζ��֭��Ʃ���֥�K�٤���
���i�Ϥ��Ǥ�ϯ�˸����Ƥ��ƥƥ�Ӥ�Ҋ�Ƥ��������ˤ��֤ä������Τ����ǸФ���ȡ�Ŀ��ǰ���ä��줿ζ��֭��Ҋ�Ĥ�ơ��狼��Ȥ�䤷�����Ƚ��ˤ˴_�J������
��������
���ؤ�����䤷��ζ��֭�Ȥ������Ҋ����
������ĸ�������Ƥʤ��ä��ä���
����䤷�Κn���������ä��ǽ��ˤ�������䤷�Τߤ�֭�����äƤ������ٻ餷�Ƥ����ĸ�����똔�ˤʤä������ǡ����ޤ�ڤˤ��ʤ��ʤä��������줬���Ĥ�����ä��Τ���ҙ���Ƥ��ʤ���ζ��֭���äơ�����ǰ��ҹ���ä��֤�����ä��Τ����ց����뤳�Ȥ϶ࡩ���뤱��ɡ�ζ�����Ϥ��٤�ĸ�����Ƥ���������ǰ�Ϥ��ޤ��ޡ��֤��դ��Ƥʤ��������ä����齡�ˤ�ζ�������������ä���
�����äƟo���ä���˼�����ɡ�����ʳ�٤褦�衣���롹
����Ԓ���жϤ�����褦�˚i��������������ˤϤޤ����å�����ä��÷Ť��ˤ��Ƥ����⤸�㤬�ȥ������֤äơ������˥Ʃ���֥�ؤȑ��롣���Ĥ⡢ĸ�ȸ�����������äƤ��ơ����ˤȚi���Oͬʿ�������ˤ��Ӥʤ��������ƶ��ˁK��������Ҫ������Τ��������ȿ����Ƥ��ޤ����㤬ֹ�ޤä������Ύڤ���ӥ��С����ˤ��O�ˁK�������Τ�����˸Ф��롣����˼�äƤ��ޤä��顢�Ӥ����Ȥ��������ˡ����Έ�����������������
���������ˣ���ʳ�٤ʤ��Σ���
��������������������
������ʽ��ˤ�Ӡ������i������Ӡ��Ŀ��Ԓ�������Ƥ�������Ȳ���Ϥ��Ĥ��ϯ�ˁK�٤��Ƥ��롣�����Ǥ⤷�����ˤ��i�Ό���ˤʤ�����С�������R�Ƥ��뤳�Ȥ˚ݸ�����롣����ʤ��ȤƤ��ޤ��С�ͬ�����Ȥ��R�귵���Θ��ʚݤ����ơ����ˤ����Ʃ���֥���ä��Ți���O�����ä���
�����O�ˤ���i�ϡ���ӥΰ¤ˤ���ƥ�Ӥ�Ҋ�Ĥ�Ƥ��������M�϶��ȡ����д���ؼ����äƤ��ơ������ߤ�����ü�g�˰���Ĥ��ʤ���ӳ�������줿д���Ҋ�Ƥ���������ʤ�Τ�ȫ���dζ���o�����ˤϡ�����⤸�㤬��ȡ��ʳ��ʼ��롣���ä��ΤϾä��֤���ä�����ζ�ϐ����ʤ��ä���������ä���������ϡ�����Ƥ��ʤ���
�����ˤ������⤸�㤬�ϡ������Ȥ���ζ���������ͣ���
�������ϣ���
������Ԓ��������졢�Τ��ԤäƤ���Τ��֤���ʤ��ä����ˤϚi��Ҋ�롣
�����Ӥ��������⤸�㤬�ϺΤ������ʤ���Ǥ��礦�������줬�֤���äƤ��Ȥϡ����ˤϤ����Ȥ����⤸�㤬�������äƤ��Ȥ���͡�
�������Ԥ��Ƥ��顢�����⤸�㤬�Ϥ����Ȥ���ζ�ʤΤ��������ȿ����z��������ˤ�쥷�Ԥ�Ҋ�ʤ����⤸�㤬�����ä��ꤷ�Ƥ����������줬�����Ȥ�����Ҏ���⤸�㤬�ʤΤ��ɤ����Ϸ֤���ʤ��������z��Ǥ����g�ˡ��i���⤸�㤬��ڤˤ��Ƥ����褦�Ǥ⤰�⤰�ȿڤ�Ӥ����Ƥ�����
���ɤ�ʤ��Ȥ��Ԥ���Τ����٤������o�������������Ӥ��ơ�ߤ�����Τ��֤��ä���
���ɤä���������⤸�㤬���֤���ʤ����ɡ����ˤΤ���ζ����˼���衣���ϡ�
����ֱ�˰����졢���ˤϷ��꤬�����ʤ��ä���Ŀ���ݤ餷�ơ����ˤ��⤸�㤬��ڤ��Ф�ͻ���z�ࡣ���㥬����Ϥ褯ζ���z�ޤ��Ƥ��ơ��ʤߤ�����n�ͤΤ���äѤ�ζ���ڤ��롣�ζȤ������Ƥ���ߤ���ǡ�ĸ���⤸�㤬�˺Τ����ʤ��Τ����֤��ä���
��������գ�ζ������혷����gߡ����Ƥ�����
�������ԤΤ褦�˅ۤ��ȡ��i�����������Ƚ��ˤ���������
��ĸ����֡��n�ͤ������Ƥ����衣�c�֤��Ȥ�����ȡ�ʳ�Ĥ��Ƿ֤ޤꤷ���z�ޤ��ʤ��������ͨ�����ΤȤ�����r���ơ��ߤ��ɰ�Ǥ����Ƥ����n�ͤ����������ɡ�ĸ����Τ��Ȥ������n�ͤ������Ƥ������������顢ĸ������⤸�㤬�Ϥ���äѤ���
�������ʤ�ۤɡ��_���˾��Ӥ��������⤸�㤬�Ϥ���äѤ��͡��⤸�㤬�äƤ����ζ�ʤΤ���˼�äƤ���
�����ˤ��Ԥä����Ȥ˼���ä����i�ϡ��⤦һ�ȡ���ˁ�ä����㥬����������߿ڤؤ�ߤ֡�����ζ�˜��㤷���Τ����i��ʳ�٤ʤ���ζȤ⡸��ζ����ζ�������Ԥä�����M��Ƥ��롣������������Ƥ��ä����Ȥ䡢����ä������Ȥ��⡢�i���Ԥä�һ�Ԥˡ����ˤ��Ɇ�������
����ǰ������ޤ��⤸�㤬ʳ�٤����Ȥʤ��Σ���
�������Ĥʼ�ͥ���������Ԥ��Τˡ�����äѤ��⤸�㤬���⤸�㤬����˼�äƤ���Ȥ����Τϡ��ɤ��������ȤʤΤ����ˤˤϷ֤���ʤ��ä����Ɇ���˼�ä��ޤތ��ͤƤߤ�ȡ��i�����Ц�ߤ���������
������ʳ�٤����Ȥ��餤�Ϥ���衹
���ؚݤʤ����¤ˡ����ˤϽ���ˤ��Ƥ������ҙ���롣���ƤϤ����ʤ����Ȥ����Ƥ��ޤä�����������Ǥ⡢�i�Τ��Ȥ�ȫȻ֪��ʤ�״�B�ǡ��ɤ������פʤΤ��⽡�ˤˤϷ֤���ʤ����ӓe���Ƥ���Τ��L���褦�ˡ����ˤϤ������֤�ȡ�ä���
�����㤭���㤭�Ȥ����n���������ä��ʤ�䤷��ʳ�٤Ƥ��Ƥ⡢�ݷ֤�������Ф�һ�����ä���
�����Ĥ��g�ˤ����i�ΙC�Ӥ�ֱ�äƤ��ơ���˚ݤ�ʹ���Τ��R¹�R¹�����ʤäƤ���������ʤˤ�ݷ��ݤ��ä��Τ��ȡ���ʳ������ʤ��齡�ˤϚi�Τ��Ȥ�˼���������ݷ��ݤ��ɤ���֪��ǰ�ˡ����ˤ�ǰ������i�ä���Ҋ�Ƥ��ʤ��ä��������餳�����ݷ��ݤ��ɤ����ʤ�ƚݤŤ��ʤ��ä��Τ�������ˡ�5�¤���Ѯ���Ԥ�줿�����Ӥ������Ԥ����~��������褯�^���Фˤ褮�롣�Ӥ����Ԥä��顢���Ӥ����Ԥ������줿���Ӥ������Ԥä��Τˡ�����������ʳ�����äƤ�äƤ뤳�Ȥ��Ц�����Ф��뤷�����ˤˡ����쩡����äƤ衹�Ȥ�����롢�i���Ц����˼�ä���
�����������ꥯ������ͨ�ꡢ���äƤ��ޤ������쩡��ۤ��Ϥä����顣�⤸�㤬�����ä�ʳ�ĤβФ꤬���ä����顣�Է������˾�һ�����Ԥ��U�ʤ��顢���ˤ�偤��줼�Ƥ�����
���Ĥä��Ԥ��С����쩡�����͡�
��������Ư�äƤ����Τ�����ӥ���i�������Ƥ��롣�������˚ݤŤ��Ƥ����������ˤϤ����Ʒ��¤ʤ��ä������¤�ۤɤΤ��ȤǤ�ʤ�������������������k����Τ��٤��浹���ä���
�����ȡ��ɤ줰�餤�dz�����������������Ȥ������衹
��15�֤��餤��
�����ˤϤ�����偤λ��ֹ����٤������r�g���ä������i����Ф���Ұ�ˤ�ȡ������ơ��ĥʤ��ԑ���_���롣С�����ܩ�����Ϥ���˥쥿����݆�Фꤷ�����奦�ꡢ�ͤ��Фä��ĥʤ�ƥ���������ä�����
�����줫��⤦һ�ȡ�偤˻�������Ĥ��Ĥ��������Ƥ��Ȥ����ǻ��ֹ�ᡢ��Τ褽�äƤ�����˥��쩡��������z��������g����ʳ�Ǥ��뤬�����ˤϳ���������֤�i���ʤ��ä�����������˼����15�֤ۤɤ���ɤ��Ƥ��ޤ�����ɡ�Ұ�ˤ���Ϥ��ä���ȳ�������L��ζ����줿��ʤ�ζ�ˤ⤳����ä������쩡������m�ޤ�Ƥ��ʤ��������B�֤⿼���ƥ������~���˳������֤��z������ȤƤ��ޤ��ȏ����ФäƤ���褦�Ǹ������Ĥ����������Ƥ��ޤä��ϒi�������֤�i���ʤ��Τ��F״���ä���
������˥�����驡��������Фǥ��쩡�ʳ�٤����ζ������͡�
�������Ĥǥ�������ͬ�����ʡ�
�����ˤ��ؤÚݟo���Ԥ��ȡ������Ĥ˥���������ζ������͡���Ц�����ɤ����ơ�����ʤˑB�Ȥ����ä��Τ����ˤ�����Ǥ��ʤ